大規模林道の呆れた費用対効果分析
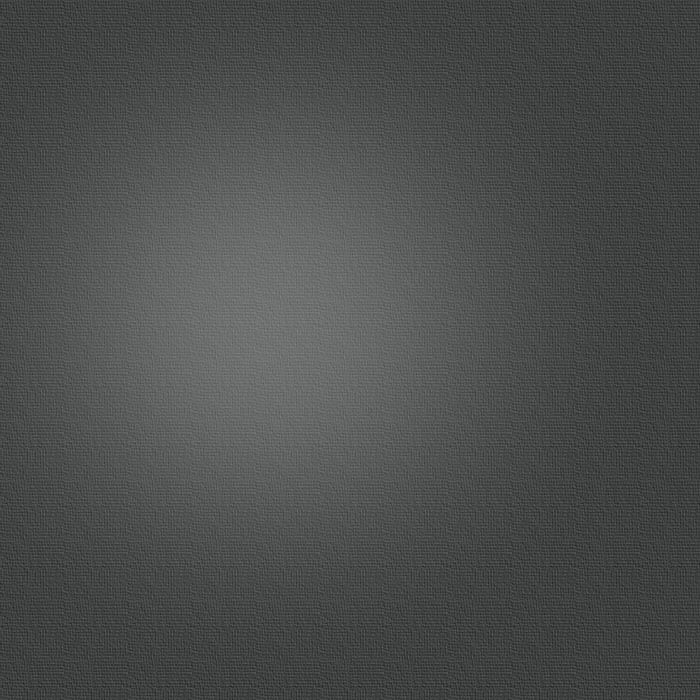
緑資源機構の前身は1956年に発足した森林開発公団である。当初、同公団が行なう事業は森林開発公団法に伴う時限立法(あらかじめ一定の有効期間を定めて制定される法律/期限を迎えると消滅または改正される)だったが、天下り先を失うことを恐れた林野庁は延命を図り、それまでの公団林道建設から関連林野事業、特定森林地域開発林道事業(スーパー林道)などと業務を増やしてきた。
その過程では当然「廃止すべき」との意見も出されたが、生き残りをかける林野庁は強引に大規模林業圏開発計画に着手。1999年の特殊法人整理合理化計画でも廃止されることはなく、農用地整備公団を併合して名称を「緑資源公団」に変更した。廃止や縮小どころか組織が肥大化しただけで終わったのだ。
その後、2002年には特殊法人から独立行政法人となり、さらに名称を「緑資源機構」へと変更。政府はこれを特殊法人改革と呼んだが、いうまでもなく現実は“名前を変えただけ”なのである(※緑資源機構廃止に伴い、同機構の事業は森林農地整備センターに引き継がれた。今回もまた「名前を変えただけ」との批判がある)。
同機構が進める大規模林道建設は、現在(2005年)の名称で正確に表記すると「緑資源幹線林道」となる。しかし名称変更によってイメージアップを図っているだけのことで、事業内容は何ひとつ変わっていない。「緑資源」などと偽装してはいるものの、日本に残された貴重な自然を分断する破壊行為であることに変わりはない。よってここでは、旧名称の大規模林道と表記してゆくことにする。
日本は世界の歴史から見ても例がないほどの借金大国になっているが、それでも大規模林道建設は続いている(2004年現在)。その理由はこの事業に充てられる予算が一般会計ではなく、まったく別の財布から引き出されているからだ。それこそが、道路公団民営化の次に注目を集めている郵政民営化議論と密接な関係にある「財政投融資」である。
その内訳は郵便貯金と簡易保険資産。これらの莫大な資金が財政投融資資金と名を変え、特殊法人や独立行政法人にばらまかれているという構図だ。緑資源機構などの独立行政法人は財政投融資を利用することが認められており、こうした法人は財投機関とも呼ばれている。これら財投機関は郵便貯金などの財政投融資を事業に充てているほかに、財投機関債と呼ばれる債券(借金)を発行することができ、これらの融資と債券で事業を進めているわけである。
その内、債券の部分はもともと借金であるわけだが、財政投融資の分にしても、郵便公社の預金者(国民)から借りているようなもの。となれば、大規模林道は借金を積み重ねながら建設されていることになる。すでに計画されている2488kmの約半分の工事が終了しており、それに使われた金額は約1兆円。いずれはこれも後世の国民が背負わざるを得なくなる、というわけだ。
※緑資源機構の廃止に伴い、未着工区間約700キロの整備は全国15同県に移管された。このため事業の継続は道県の判断による。ちなみに北海道や岐阜県は継続見送りを決定、岩手県は継続する意向のようだ。
林野庁の天下り先『緑資源機構』

大規模林道でたびたび目にする法面崩壊。岩手県内の川井・住田線、横沢・荒川区間では降雨のたびに崩れているという。しかし完成後の維持管理費は関係自治体が負担することになる