ダム建設による河床低下と河岸崩壊2/5
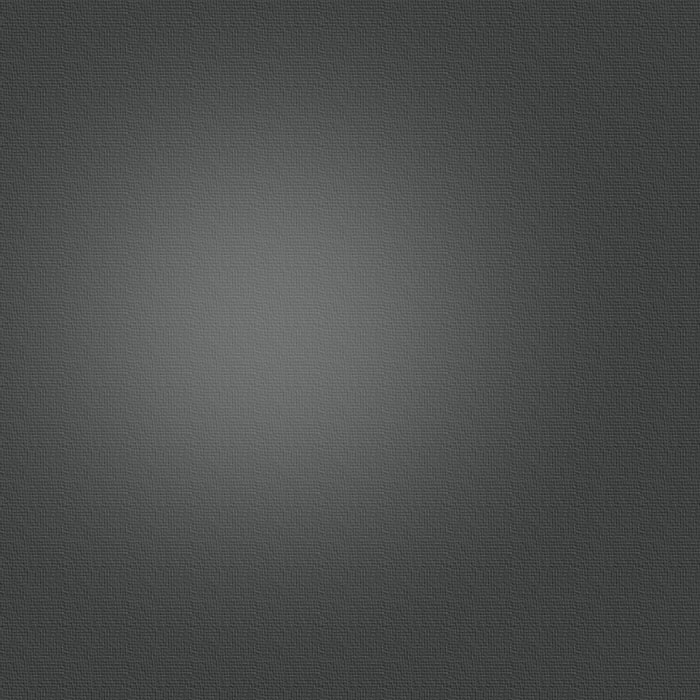
スリット化の事例はすでに全国各地で報告されるようになった。しかし堆積していた土砂が下流に流出することから、その影響を懸念する声があることも確かだ。またその懸念を理由にスリット化を拒む事例も報告されている。これもまた北海道が舞台である。
道南地方の須築川において、沿岸の漁業者らがスリット化を要望していることは前号でもお伝えした。漁業者らはダムを管理する函館建設管理部から「スリット化は下流にヘドロが出る」と説明を受けたが、それでも「5年や6年は我慢する」「漁業補償もいらない」から「川を元に戻してほしい」と訴えてきた。
一方で函館建設管理部は説明のなかで、「ヘドロは産廃の扱いになり、処理費用がかかる」と主張したというが、これは筆者にとっても寝耳に水だった。そのような論理をダムを管理する行政が主張するとは、想像もしていなかったからだ。確認のため函館建設管理部に問い合わせると、やはり同様の主張が飛び出した。「ヘドロを下流に流すと産業廃棄物処理法違反になる可能性がある」というのだ。
では、富山県の黒部川はどうなのか。関西電力は出し平ダムの排砂により大量のヘドロを下流に流出させた。また国交省も宇奈月ダム(出し平ダムの下流に位置する)の排砂ゲートを開放し、両者は沿岸漁業に壊滅的な影響を与えてきた。函館建設管理部がスリット化による土砂の流出を産業廃棄物処理法違反だとするなら、関西電力と国交省はまさにその張本人となるわけだ。これはダム行政全般に関わる重要な発言だと見なされるべきだろう。
ちなみに砂防ダムおよび治山ダムのスリット化において、ダムに貯まった土砂が下流に悪影響を与えたという報告はまだ聞こえてこない。規模が小さいことがその要因といえるが、このことで大規模な多目的ダム(貯水ダム)と同一視すべきでないことが分かる。
最もスリット化が進んでいるのは山形県内の国直轄砂防ダム群だと思われるが、スリット化後はむしろ「水がきれいになった」との声を聞く。ちなみに山形におけるスリット化の事例は、大半がダム最下部までスリットを入れておらず、魚類の移動は困難なものが多い。スリット化を実施した理由は水質悪化を改善させることが目的だったという。
このほか北海道の事例と酷似しているのが青森県の津梅川である。ダムが海から数kmの位置にあることや上流部の森林の状態(津梅川の源流域は白神山地)、サケ科魚類が溯上するという点で共通している。スリットはダム最下部まで入れられ、貯まっていた土砂は当然下流へと流出した。しかし沿岸に影響が出たという報告はなく、現在ではサケが溯上できるようになったという。
このほか北海道の事例で興味深い調査結果がある。北西部の留萌管内において満砂した治山ダムの切り下げが実施され、その後の土砂移動について調査しているのだ(幅の大きなスリットを最下部まで入れた)。
その中の記述には「切り下げ以前はダム直上には細粒分が集積し、ダム下流では露盤化が進行していた。切り下げにより、渓床堆積物の粒径の偏在が解消された」とある。つまりは「細粒分が集積」「粒径の偏在が解消」との記述から、ダムが土砂をふるいにかけている実態を研究者らが認識していることになる。裏を返せば満砂ダムも河床低下を引き起こし、かつスリット化によってそれが解消されることを証明しているのだ。
もちろんスリット化によってすべてが解決するとは限らない。スリットの幅によっては流木が詰まるなどの問題も残されているからだ。しかし魚道を設置するよりは遥かに有効であり、河床低下の問題も軽減される可能性が高いといえる。
また近年では、従来の砂防ダムのように河川を横断する構造物ではなく、両岸から交互に構造物が伸びた水制ダムなる新たな砂防ダムも考案されている。これは魚類の移動を阻害することもなく、また平水時における土砂の移動もあり、今のところベストな選択のように見える。筆者の知る範囲内ではまだ山形県内に1基のみ(最上川水系立谷沢川)。これが次世代の砂防ダムとして確立されれば河川環境も改善しそうだが、残念ながらまだ調査段階で普及には至っていない。今後の調査研究、そして環境と防災を両立させるための一層の努力に期待したいところである。
既設ダムのスリット化は有効か




北海道、道南地方の須築川では、沿岸の漁業者らが砂防ダムのスリット化を要望している。しかしダムを管理する函館建設管理部は2011年現在でもまだスリット化を拒み続けている
山形県内の荒川水系玉川支流内川の砂防ダム。かつては旧来式のクローズダムだったが、下流部の水質悪化を軽減させるためスリット化の工事が実施された。工事後、下流部には堆積していた土砂が流下したものの、水質はむしろ改善したという
青森県・津梅川。スリットは最下部まで入れられ、改修後貯まっていた土砂は無論下流へと流出した。しかし沿岸に影響が出たという報告はない。サケの遡上が確認されているようだが、コンクリートの床が残された関係上、小型魚類の遡上は極めて難しいと思われる
近年建設された山形県・立谷沢川(最上川水系)の砂防ダム。従来の砂防ダムのように河川を横断する構造物ではなく、両岸から交互に構造物が伸びるのが特徴で、水制ダムと呼ばれる。魚類の移動は当然可能であり、また礫の移動にも大きな影響は及ぼさないと考えられる(写真/国土交通省提供)