ダム建設による河床低下と河岸崩壊4/3
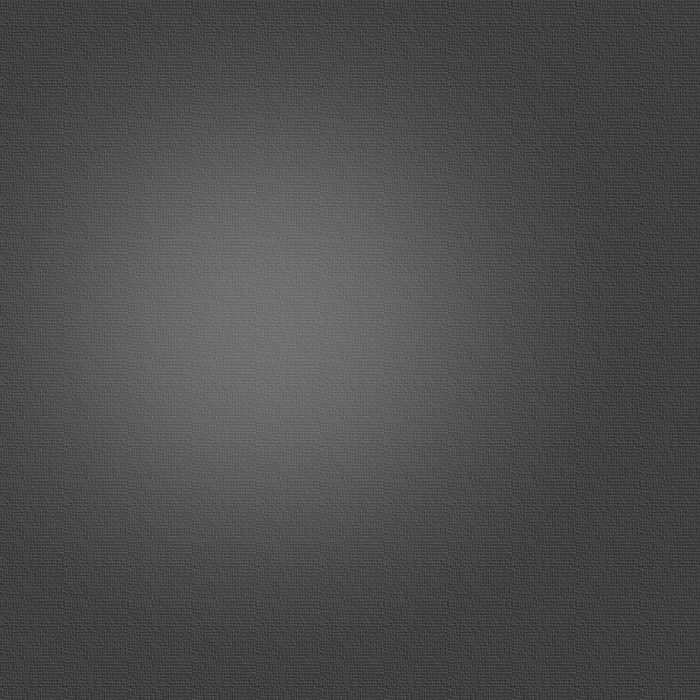
重ねて述べるが、真駒内川での礫床化実験は根本原因に手をつけることなく実施された。裏を返せば、この真駒内川において礫河床復元の可能性はまだ多分に残されているといえる。上流にあるのは貯水ダムではなく砂防ダムのため、スリット化など礫を下流に流す改修が可能だからだ。
2011年9月の出水時には実験設備だけでなく斜路工(低ダム)や護岸も被災。人工構造物がことごとく流されただけに、河川管理者と関係した学識経験者は完全に面目が潰された形となった。原因は誰の目にも明らかで、河床は最大で約3mも下がっている。土砂供給の改善が急務であることはいうまでもない。
被災した斜路工は改修される以前、魚類の遡上が不可能な落差工(堰堤)だったという。それを流域住民らを交えた協議により、魚類が遡上できるよう斜路工に改修した経緯がある。改修年次は平成21年。わずか2年あまりで道民の血税が消えたことになる。
被災原因について北海道札幌建設管理部は「上流から大きな岩盤が河床から剥離してきて被災してしまった」と言う。流れてきた岩盤の大きさは長さ約4.5m、幅約2.5m、厚さ約0.5mと巨大なもので、これが斜路工に激突した可能性があるという。その直接的な衝撃で崩れたのかは分からない。あるいは斜路工上流部が岩盤の剥離により深く掘り下げられたことで、余計に水圧がかかったとも考えられるだろう。確かなことは、真駒内川における河床低下および露盤化がいかに深刻であるか、その現実を如実に物語っていることだろう。
しかし厳しい見方をするなら、落差工を斜路工に改修しようとしていた当時からすでに、河床低下は深刻な状況にあったはず。それでもなお土砂供給の改善(砂防ダムのスリット化など)に着手することなく、魚類が遡上できればそれでよしとする安易な工事が実施されたともいえる。学識経験者が協議に加わっているにもかかわらず、である。
こうした反省から、2011年12月1日には学識経験者と流域住民らを交えた『平成23年度第一回・真駒内川対策協議会』が開催され、今後の対策は目下検討中とのこと。河川管理者も河床低下の問題を深刻に受け止めているが、まだ具体案は出ていない。
真駒内川の現状を知る『NPO法人真駒内・芸術の森緑の回廊基金』の新田啓子さんは言う。
「土砂の供給がなければ再び失敗することにもなりかねません。そこで砂防ダムのスリット化を要望しているところですが、河川管理者からはまだ前向きな回答は得られていません」
こうした意見に対し、北海道札幌建設管理部は「検討中なのではっきりとしたことは言えない」としながらも、「砂防ダムのスリット化もひとつの方法」とし、スリット化を完全否定しているわけではないらしい。ただし、「被災した施設は年度内(2012年3月まで)に応急的な対策を行う予定ですが、河床低下の抜本的な対策はもう少し時間がかかると思う」としている。
計8基あるといわれる砂防ダム、そして約2kmにも及ぶ流路工(低ダム群)、その改修なくして根本的解決には至らないはずなのだが、なかなか前向きな議論にならないのが現状のようである。
出水時に流される人工構造物

平成21年度の工事が斜路工が整備されたものの、2011年9月の出水時に被災。露盤化した上流部の河床から大きな岩盤が剥離し、斜路工に激突したと見られている

露盤化区間と砂防ダムの間には低ダムが連なる流路工が約2kmと広い範囲に続いている。これもまた掃流力(土砂を運ぶ水の力)を弱めている関係上、河床低下の原因となり得るはず。早急なる改修が望まれる

流路工(低ダム群)の改修事例としてお手本的な存在が長野県の牛伏川にある。真駒内川の今後においても参考になるはずだが・・・