大規模林道の呆れた費用対効果分析
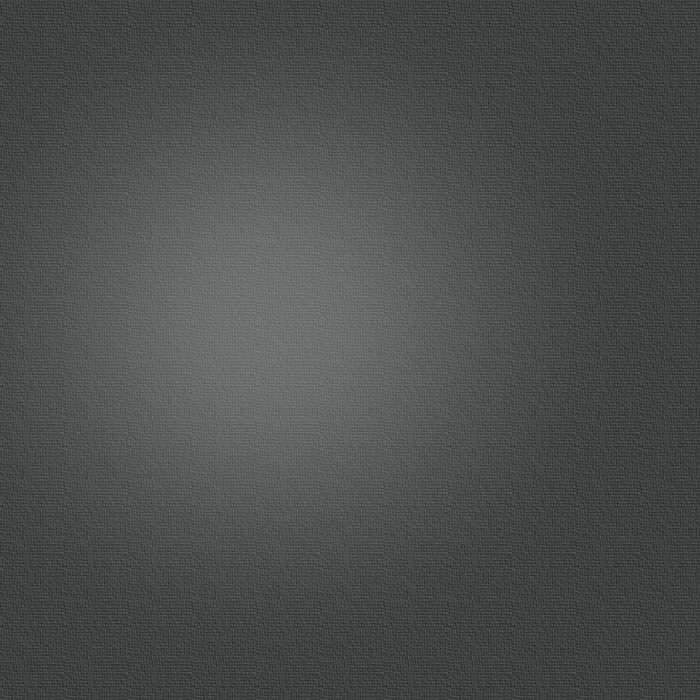
林道とは名ばかりの自然破壊道路
登山者を含む自然保護関係者の間では、古くからとある道路建設問題に異論の声が上がっていた。それが7つの森林地帯に2488kmもの林道を建設するという「大規模林業圏開発事業」(後に緑資源幹線林道事業)であり、一般に大規模林道と呼ばれる事業である。
事業主体は林野庁所管の独立行政法人『緑資源機構』(官製談合事件を発端に平成19年度で廃止/現・森林農地整備センター)。ひと言で林道といっても、その規模はとても林道とは思えない代物。原則として幅員7mの2車線、しかも全面舗装であり、大型の観光バスが余裕で通行可能な立派な観光道路なのである。ところが山岳地帯に建設されるという性格上、通行量は非常にまばら。例えばある区間では、道路の真ん中で弁当を広げてくつろいでいても何ら支障がないほど。実際にそのような場面に出くわしたこともあるが、自動車が通ることの方が希なのだから、その人たちに文句を言う気になれないのが実情だ。
ではなぜ、利用価値の低い大規模林道建設を推し進めてきたのか。林野庁と緑資源機構は建設目的について、「7つの林業圏域には全国の森林の30%にあたる約750万haの森林があり、幹線林道を軸とする林道ネットワークは、水の供給や地球温暖化防止など森林の持つ機能をより多く発揮させるだけでなく、山村地域の生活道路や都市と森林を結ぶパイプラインとしても役立ちます」とする。また地域の活性化や災害時の迂回路などの機能が強調されることもある。
しかしながら現在の林業は、通常の林道が整備されている地域でさえ手入れを怠った放置人工林である。外材の輸入で木材価格が暴落し、また高齢化によって物理的に作業が不可能になっているのが現実なのだ。
そこに新たに立派な林道を建設したとしても、人手がないのだから林業活動が再開されるとは考えにくい。仮に外材輸入が滞って日本の林業が復活するとしても、既設の小規模な林道が日本の森林には縦横無尽に通っているのだから、それで十分だろう。まして7mの完全舗装路が必要なはずもない。
結局のところ、大規模林道建設の目的は地球温暖化の防止でも林業の再建でもなく、無論地域の活性化といったものでもない。むしろ土建業者の活性化と役人の天下り先の確保、この2点が緑資源機構の目的だったと断言してよいだろう。苦し紛れに災害時の迂回路を持ち出す区間もあるにはあるが、現実は災害時になれば真っ先に通行不能になるのが大規模林道なのである。(次のページへ続く)
注)月刊つり人別冊「渓流2005夏号」に掲載した記事のため、現在の状況と異なる部分が多くあります。補足として部分的に加筆しておりますが、その点熟慮下さるようお願い致します。
