『ダムが渇水を引き起こす!』
という論文の、驚くべき内容
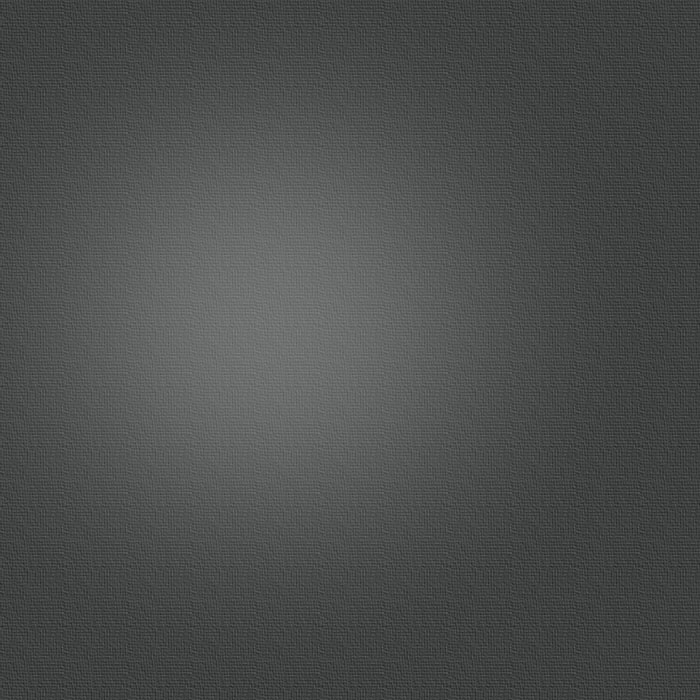
『ダムが渇水を引き起こす!』
という論文の、驚くべき内容

水余りの現実のなか、建設が進む多目的ダム
全国のあらゆる河川に建設されてきた多目的ダムの建設目的は、主に「治水」と「利水」に分けることができる。治水とはいうまでもなく洪水調節を意味するが、一方の利水は水資源開発のことであり、これは主に水道用水や農業用水、工業用水の確保などが挙げられる。また、近年下流部からの要望によって流量の増加が実施されるようになってきた「維持流量」(注1)も、利水目的のひとつと呼んで差し支えないだろう。
このほか建設目的には発電が含まれる場合もあるが、水を利用しているという点ではこちらも利水。よって建設目的を大きく分けるなら治水と利水になるのだが、後者の水利用は多岐にわたることが分かる。ダム問題の是非を問う議論では、これら建設目的に対してさまざまな検証が行われており、推進派、反対派の主張は今も平行線のままである。
ダム問題が語られる時、近年は治水目的がクローズアップされる傾向が強い。しかしダム建設の歴史を見ると、むしろ利水目的が主役だったといってよい。右肩上がりの人口増が見込まれた高度経済成長期以降、水資源開発を推し進めることが第一の目的とされてきたからだ。
ところが人口減が現実となった今、もはや水余りが顕在化しているのが現実。しかも地方自治体の水道事業はまさに火の車状態にあり、水道料金の値上げでしか対応できなくなっている。原因はいうまでもなく、なかば強引に押し付けられたダム建設費にある。地方自治体は建設費の一部を支払うことが受益者負担として義務づけられており、その負担が重くのしかかっているわけだ。
節水の取り組みが遅々として進まないのもこのためだ。仮に人々の節水意識が高まって水の使用量が減少した場合、困るのは自治体。水道事業の崩壊はすぐ目の前まで迫っているからだ。建前上は節水を勧めているかのように見えるものの、使用量が減ると困る、これが本音なのである。
こうした現状により近年は「もう水はいりません」とダム計画に参画しない自治体も出始めている。その結果利水計画が頓挫し、治水専用ダム(穴あきダムなど)がもてはやされることになる。
それでも水資源開発という名のもと、多くの流域でダム建設は続行されている。節水の取り組みもほどほどに「記録的な渇水になったらどうするんだ」と危機感を煽り、また国交省など事業主体のパンフレットやホームページには必ずといってよいほど、「ダムがあればいつも安定した水が流れますよ」とダムの必要性をアピールするイラストが掲載される。しかし、本当にそうなのか。
ダムがあれば下流部は水が滔々と流れ、水不足を解消してくれるという理論。これを単純に考えてみると、上流(森林)からの流量が減少しても、ダムに水を貯めることで水を徐々に供給できますよ、となる。森林からの流出量は気候によって変動があることから、その分をダムの水で補うと考えれば分かりやすい。つまり、森林からの水のみだと季節によって流量に変化が出てしまうものの、ダムがあればその変動を最小限にできるというわけだ(ダムの流況平準化効果と呼ばれる)。年間の流量が安定すれば、下流部の街も安心して給水できるというのがダム管理者の主張なのである。
しかし、そんな単純な論理で流量のコントロールが可能なものなのか。洪水調節においてもゲート操作の難しさが指摘されているだけに、ダム貯水池が渇水を緩和する機能もゲート操作に左右されるはず。となれば、流量を安定させると言葉にすれば簡単な作業も実は生易しいものではない。
その疑問は随分と前からあったのだが、実は1998年に調査検討された論文が学会に発表されていたのである。
下流を潤すといわれていたダムが、実は『渇水を悪化させていた』とする論文がある。1998年に水文・水資源学会誌に掲載されたが、その話題は学会内で語られるのみで、広く一般に知られることなく時間だけが経過していた。利水目的上、ダムは不要であるとの結論に達する重要な研究論文といえる。
(写真は二瀬ダム)
注1)維持流量とは、平常時において下流に流すべき流量のこと。治水、利水とは別に「流水の正常な機能の維持」と呼ばれることもあり、建設目的のひとつに掲げる場合もある。近年では内水面漁協など下流部から維持流量の増加を求める声が拡大しており、水利権更新時に若干ながら増加される河川も報告されている