『ダムが渇水を引き起こす』という論文の驚くべき内容
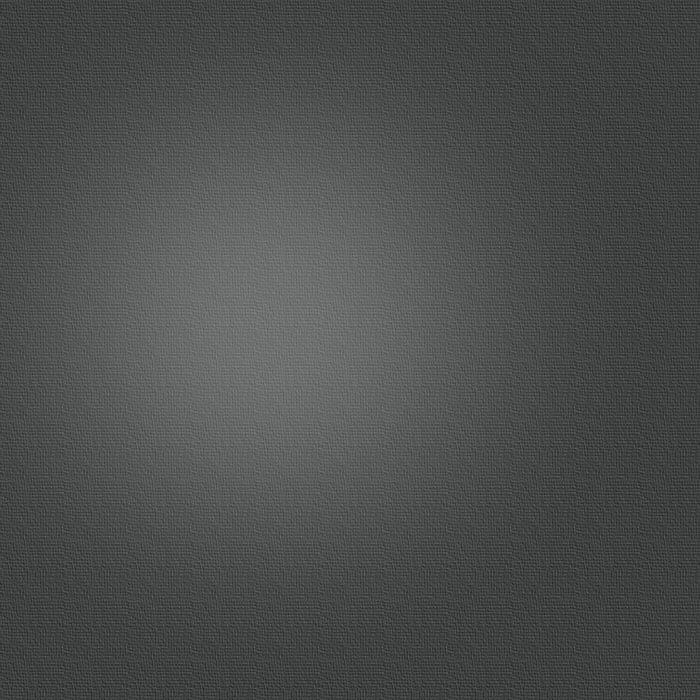
1998年、水文・水資源学会誌に掲載された論文『森林流域におけるダム貯水池の流況平準化効果の評価』では、森林からの流出量とダム貯水池からの放流量を対比し、ダム貯水池がどの程度渇水を緩和できるのかを検討している。
対象としたのは、人口が集中し安定した水の供給が重要と考えられる関東地方の11流域。森林とダムとの対比を分かりやすくするため、それら11流域の最上流部のダムにおいて流況平準化効果を評価している。流況平準化効果とは、森林からの流出量が減少する際、ダムが流況(流量)を安定させる機能と考えればよいだろう。
森林からの流出量は無論時々刻々変化するわけだが、ダムはそれを補って下流に流れる流量を安定させなければ意味がない。それを学術的な流況解析法によって調査したというわけだ。
ちなみに各流域の日雨量や日流量の記録は、建設省所管の水資源開発公団(当時:現・国土交通省所管の独立行政法人・水資源機構)発行の多目的ダム管理年報より得ており、5年間のデータを値の順に並べ替えた後、単年の記録と対比できるようにしているという(5年間のデータを1年間に変換したと考えればよい)。
これらのデータから、森林の流出量とダムからの放流量をそれぞれ流況曲線で表し、その比較によって流況平準化効果を割り出すという手法である。また、論文では観測期間中の最小降水年の流況曲線についても触れており、5年間のデータから調べたものを「平年」、最小降水年のみのデータを「渇水年」と定義している。
調査したダムは有間ダム、下久保ダム、二瀬ダム、小河内ダム、三保ダム、相俣ダム、五十里ダム、川俣ダム、草木ダム、薗原ダム、中禅寺ダムの11箇所。関東近県の方なら、いくつかのダム名は耳にしたことがあるはずである。
論文を発表したのは東京大学大学院農学生命科学研究科所属の久米朋宣さん。調査を始める当初は久米さん自身も、ダムは変動する森林からの流出量を安定させ、年間を通じて一定の水を使えるようにするものと考えていたようだ。ところが、結果的には正反対のデータが出てきてしまったという。
「この研究では、時々刻々変化する流量を分かりやすくするため、値の大きいものから小さいものへと順番に並べ替える作業を行っています。つまり森林からの流量が減少した時の分をダムが補っているとするならば、大小の差が縮まることになります。流量が多い時と少ない時の差が縮まる。当然そのような結果になると思ったのですが、実際に並べ替えてみるとどうもダムの方が低くなる、渇水をより厳しくさせているというデータが出てきました」
流量を安定させるはずのダムが渇水を引き起こす。あってはならないことが起きていたのである。
ダムは必要なかった、という結論
平年時の調査では、11基のダムのうち10基が渇水を悪化させていた。つまり利水目的上、ダムは必要なかったことになる。またダム貯水池の水は有効に使われていないこと、そして人為的な放流(ゲート操作)がいかに難しいか、その現実を露呈した結果ともいえる
