『ダムが渇水を引き起こす』という論文の驚くべき内容
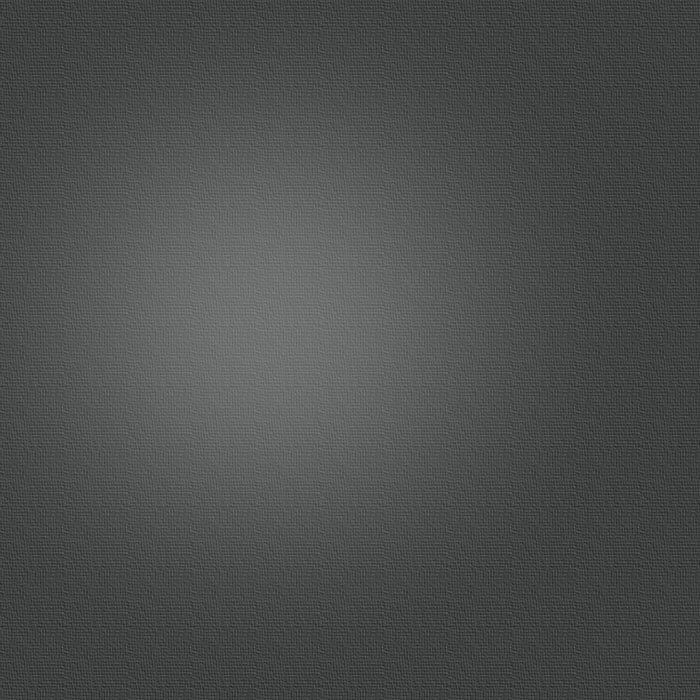
まずは観測期間内で最も降水量が少なかった昭和59年のデータを見てみると、調査した11流域のうち、ダムが流況平準化効果を発揮していたのはわずか5流域のみ。あとの6流域は、ダムがあることで渇水を悪化させてしまったのだ。
11基のダムの内、5基が機能を果たしていたから良しとする・・・と、まさかそんなわけにはいかないだろう。莫大な予算をつぎ込んで建設しているのだから、11基すべてが機能しなくてはならないはずだ。
しかも渇水を悪化させていた6基の内、荒川上流部の秩父山系にある二瀬ダム(昭和36年完成)は、森林に対してダムの流況曲線の悪化部分が年間にして約300日分にも及んだという。つまり、森林から出てくる流量よりもダムからの放流量が少ない期間が、約300日間も続いていたことになる。しかもこれは最小降水年のデータ。最も水が欲しい時にダムが機能しなかったのだ。
ちなみに渇水を緩和していなかったダム、渇水を悪化させていたダムは二瀬ダムのほか有間ダム、川俣ダム、薗原ダム、五十里ダム、小河内ダムの6箇所。これらのダムは利水目的上必要なかったことになる。
半数以上のダムが機能しなかったことについて、久米さんは次のように話す。
「原因がどこにあるのか、そこまでは分かりませんが、例えば二瀬ダムの事例でいえば、この年は(放流)制限をかけすぎたのかもしれません。それこそ、その年に降った雨を翌年に持ち越すくらいの、そんなゲート操作をしていたようですね」
洪水調節において度々問題視されているゲート操作の難しさ。それは利水目的においても同様のことがいえるようだ。ダムによっては取水設備が複雑な場合もあるため、ゲート操作という言葉は適当ではないかもしれないが、いずれにせよ人為的な放流、放流量の調節は決して容易でないことが分かる。水が必要な時に放流せず、必要ない時に放流してしまっている、と考えれば分かりやすい。結果、ダムが無いほうが水不足にならないという結論に達してしまうのである。
ただし驚くのはまだ早い。昭和59年に限定したデータでは、ダムが機能しなかったのは11流域中5流域だが、5年間の計測から割り出した平年データの場合、さらに多くのダムが機能していないことが分かったのである。
平年データによればダムの平準化効果が発揮されたのは11流域中わずか1流域。あとの10流域はダムによって、より渇水が悪化していることが分かったという。掻い摘んでいうと11流域中で10の流域では、森林のみで十分だった(ダムはいらなかった)というわけだ。しかも興味深いのは、辛うじて平準化効果を発揮したダムが中禅寺ダムであるということだ。
中禅寺ダムの高さはわずか6.4m。貯水池はあの中禅寺湖である。自然湖なのだから貯水池と呼ぶのは違和感を感じるが、ダム管理者がこの自然湖を貯水池と見なしているのは事実であり、その出口にある水門程度の小さなダムのみ、渇水を緩和する機能があったという。
しかもそれが皮肉に感じてしまうのは、他の10流域における人工のダム貯水池が機能せず、自然湖が機能してしまったという点である。極論、自然の湖は渇水を緩和する効果を保持していたが、人工の湖(ダム湖)はむしろ悪化させていたのだ。
巨額を投じて巨大なダムを建設しておきながら、そのほとんどが渇水を生じさせ、渇水を緩和させることができたのは自然の湖だけだった。結局、ダムなど建設することなく、自然のままにしておいた方が下流部は潤うのだということを、この調査は実証してしまったのではないか、そんな気がしてならない。
そして行き着くところはやはり、ゲート操作の難しさなのである。 (次のページへ続く)
水不足を軽減していたダムは11基中わずか1基


荒川上流部の二瀬ダム(昭和36年完成)は、調査結果で流況平準化機能が最も低かったダムである。森林から出てくる流量よりもダムからの放流量が少ない期間が実に約300日間も続き、渇水を軽減するどころか悪化させていたという
11基中、唯一機能したのが中禅寺ダム。ダムの高さは6.4mとされているが、実際にはそれほどあるように見えない。貯水池はあの中禅寺湖である