『ダムが渇水を引き起こす』という論文の驚くべき内容
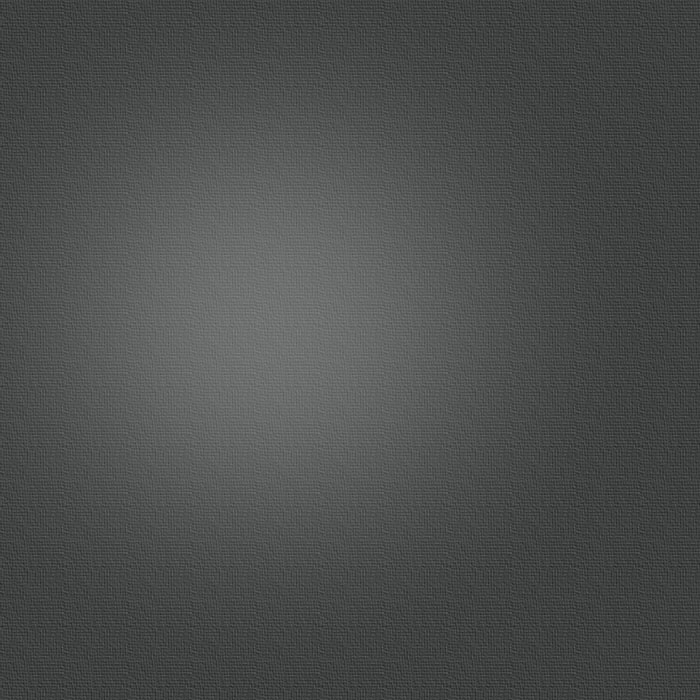
ダム建設の歴史を紐解いてみると、水力発電が主流だった時代には発電専用ダム(電力会社所有)が建設されることも多かったのだが、昨今のダム計画といえば大半は国交省(旧建設省)や都道府県が事業主体となる多目的ダムである。この場合、治水(洪水調節)と利水(水道用水、農業用水など)といった相反する機能を兼ね備えることが前提となり、その矛盾を抱えたままゲート操作を行わなければならない。ダム貯水量は一応、洪水調節容量と利水容量とを分けてはいるものの、ゲートの開閉操作を行うのは所詮人間であり、理論どおりにはいかないのが現実だといえる。
例えば多くのダムで、降水量が多いシーズンに備えて事前に水位を下げておく、といった作業が行われている。台風の接近によって多量の降雨が予測される場合、洪水調節のためにゲートを開放して水を放流しておくのである。しかしもし予測どおりの雨が降らず、その後も日照りが続いてしまったら、ダムの貯水量は一向に増えない。
また反対に、長期予測で雨が降らないと判断された場合、ダム放流はなるべく控えて渇水に備えることもあるだろう。すると下流部は減水したままの状態が長期間に及んでしまうことになる。
同じ利水目的の範囲内でも、水の利用状況は大きく異なる。市街地が必要とする水道用水と、電力会社が使用する発電とは必ずしも放流のタイミングが一致するとは限らない。市街地に水を送りたいと考えても、その前に発電目的で大量の水を使用してしまっていたら、下流部の水不足は解消されないことになる。
ダム推進派が度々口にする「ダムがあれば一年中水量が安定しますよ」といった主張、結局はそれも気象予測頼み。予測が外れると期待どおりの機能を発揮できないわけだ。この研究論文は、その現実を的確に示しているといえる。
「ここでは洪水調節機能の評価はしていませんし、水系の最上流部のダムに限って調べていますから、ダムが無くても大丈夫、ということまでは言えません。ただし水不足量の比較をすると、多くの流域で(ダムがなくても)森林のみで十分だということになります。また、こういった比較そのものが今までなかったので、公表する価値はあると考えました」
久米さんはこのように話すが、利水目的に限定した調査とはいえ11流域中10流域でダムがない方がマシ、森林で十分だというのだから、まさに驚くべき結果である。いったいなんのためのダムなのか、改めて考えさせられる研究論文だといえる。
もちろん同研究ではダムの必要性云々までは言及していない。しかし最も水需要が増加すると考えられる夏季だけで考えても、いつから渇水に備えて水を貯めるか、あるいはいつから洪水に備えて放流するのか、その判断は難しい。結局、多くのダムは矛盾を解消できないままなのである。 (次のページへ続く)
人為的ゲート操作の限界を露呈

ダムが下流部を潤すという神話は崩れ去った。調査結果では流況平準化効果を発揮したのは中禅寺湖のみ(平年時)。皮肉なことに、巨額を投じて巨大なダムを建設しておきながら、渇水を緩和させることができたのは自然の湖だけだったのである