ダム建設による河床低下と河岸崩壊3/1
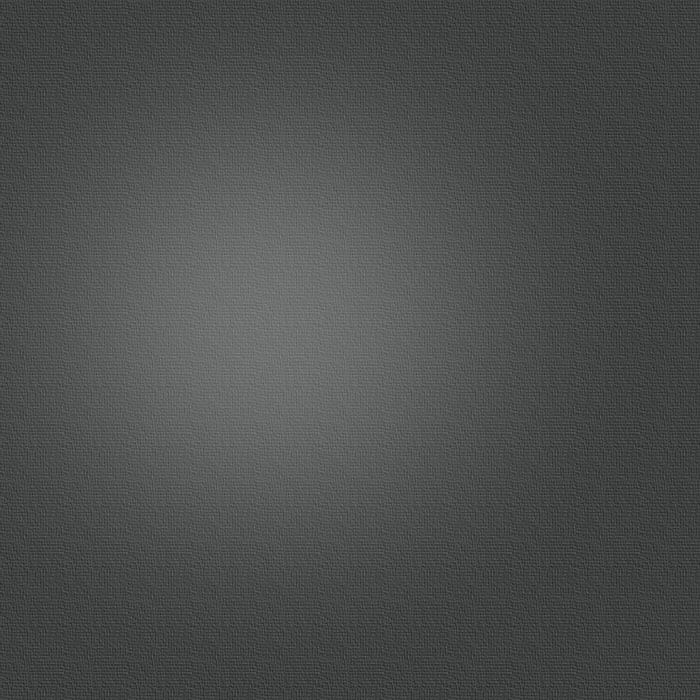

論文が伝える鬼怒川の露盤化現象
砂防ダムや治山ダム、多目的ダムなど河川横断工作物が建設されると、ダム下流部では土砂の供給量が減少することで河床が低下する。このことは以前にも述べた。本来河川における河床の高さ(標高)は、上流から流下してくる土砂と下流に流出する土砂によってバランスが保たれている。ところがダムは上流からの土砂供給を遮断し、ダム下流部の河床は洗堀によって低下することになる。結果、護岸や橋脚の根元部分が深くえぐられ、増水時にはついに崩落するといった二次災害すら発生しているのだ。
河床低下がさらに進行すると河岸崩壊を招く。そのメカニズムは次のとおり。河床が低下することで河畔林の根元部分が浸食され、これらの樹木は次第に河川に覆い被さるように傾いてゆく。洪水発生時には河畔林そのものが流出。瀬や淵が連続していた変化に富んだ流れは、次第に開けた単調な渓相へと変貌してしまうのだ。
さらに深刻なのが『露盤化』と呼ばれる現象。上流にダムがある以上河床低下はとどまることを知らず、最終的には河床の土砂が皆無となる露盤化を引き起こす。露盤化とは河床の基質である岩盤が露出することであり、河川に生息するすべての生物に対し負の影響を及ぼすことはいうまでもない。しかしながら、露盤化が河川生態系に大きな影響をもたらす反面、ダム技術者ら専門家の間で注目されることはあまりなかった。
ところが今年、『鬼怒川の黒部ダム下流における河床の露盤化』と題する論文が土木学会論文集に掲載されたのだ。この論文が掲載された意義は極めて大きい。ダム建設による河床低下が最終的に露盤化を引き起こす現実を、土木学会自らが認めたことになるからである。
執筆者は独立行政法人水産総合研究センター・増養殖研究所内水面研究部主任研究員の中村智幸さん。同氏は土木系研究者ではなく水産系研究者。土木学会誌でありながら、水産系研究者の論文が掲載されるのは希有な例といえる。ダムによる露盤化という題材である以上、本来ならば土木系研究者が調査しなければならない案件のはずだが、造る側の人々はダム建設に対し不利になる研究をなかなか行おうとはしない。また、そうしたしがらみのない水産系研究者なればこそ、露盤化の問題点にいち早く気づいたといえるかもしれない。

鬼怒川本流の黒部ダム直下。かつては礫床化(土砂が堆積)していたというが、現在は岩盤が剥き出しとなった露盤化河床となっている