最上小国川ダム建設問題のゆくえ
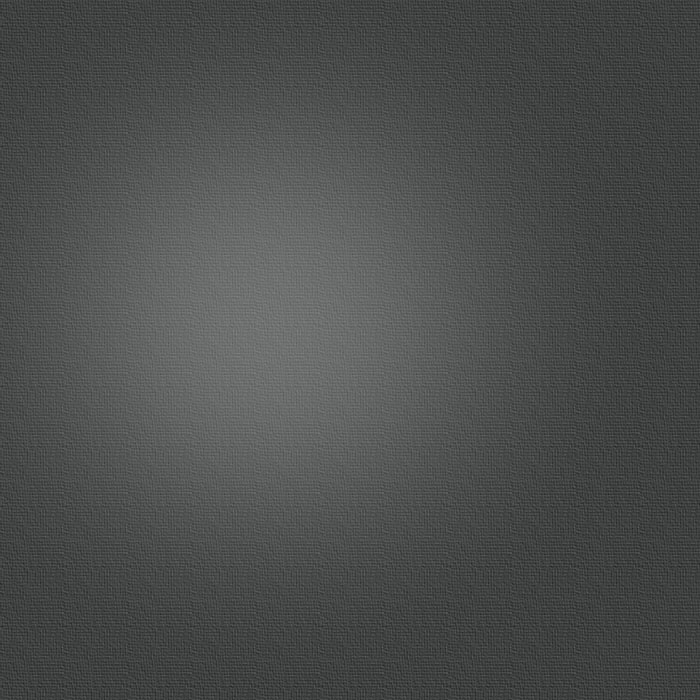

『ダムムラ』に反旗を掲げた研究者
全国のダム計画はことごとく息を吹き返しつつある。すでに国民の多くがその名を知るまでになった群馬県の八ッ場ダムを筆頭に、官僚の操り人形に成り下がった民主党はマニフェストをなにひとつ実行することなく、正反対の政策を採り続けている。そして息を吹き返したのは国の直轄事業にとどまらない。国の補助事業として県が事業主体となるダム計画もまた、役人の思惑通りに事が運びつつあるのだ。
平成23年8月、吉村美栄子山形県知事は懸案となっていた最上小国川における治水対策として、最上小国川ダム建設を推進すると発表した。その結論に至るまでの経緯として県は、様々な委員会(最上川水系流域委員会や最上地区小委員会など)において、有識者や住民も交えた検討の結果としている。しかしその検討とは、原発事故で顕在化した『原発ムラ』と同様、いわゆる『ダムムラ』内の議論にすぎないといわれてもやむを得ないものだった。
当初、最上地区小委員会の委員を務めていた沼澤勝善小国川漁協組合長も「議論は初めからダムありきだった」として第4回以降委員を辞退している。そのまま委員として議論に参加した場合、ダムムラの住人に仕立て上げられると危惧したからだ。そしてもうひとり、ダムムラに反旗を翻した人がいる。川辺孝幸山形大学教授(地質学)その人である。
川辺教授は2008年、県の依頼を受ける形で赤倉温泉の源泉を調査した。最上小国川ダムは主に赤倉温泉の治水対策が建設目的とされ、河床掘削が最も有力なダムの代替案と目されてきた。しかし河床掘削は赤倉温泉の源泉に影響を及ぼすとの指摘があることから、地質の専門家である川辺教授に白羽の矢が立ったのである。
同教授が源泉への影響を調査した結果、確かに「源泉の量や水温に影響が出る」ことが判明したという。県に対する報告書にはその旨を記載するとともに、同時に「影響は出るが対策は可能」としていたのだ。対策が可能であるなら代替案として十分な可能性がある。ところがダム建設に固執する県は報告をねじ曲げ、「源泉に影響を与えることから河床掘削は不可能」とし、穴あきダム案による治水を半ば強引に決定したのである。
県に対し不信感を募らせる川辺教授は現在、『最上小国川の清流を守る会』共同代表を務める。反旗を翻したのだ。おそらく県はダムムラ住人の御用学者らと同様に、いかようにでもコントロールできると勘違いして調査を依頼したのだろう。しかし川辺教授は目の前の事実に忠実な生粋の研究者だった。ダム建設という名の工事が欲しい県側からすれば、大きな誤算だったといっていい。
2011年11月27日、守る会主催によるシンポジウム「県民による緊急再検証!最上小国川ダム」が開催され、川辺教授を含む有識者による問題提起がなされた。同時に赤倉温泉付近の現地視察も実施され、河床掘削が可能であることを確認している。
実はこのシンポジウム、草島進一県議(守る会共同代表)によれば県職員も参加する予定だったという。ところが当日になってドタキャン。つまり逃げ出したのだ。山形県議会では相も変わらずダムの必要性を唱えているようだが、草島氏以外の議員や知事はだませても、問題点を把握している当シンポジウムの参加者そして専門家らには太刀打ちできない、そう判断したに違いない。ダム建設を進めようとしている当事者が論理的な話し合いに参加できない現実を見ても、いかに正当性を欠いた計画かを物語っているといえよう。